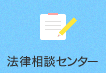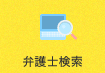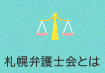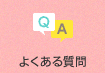「結婚の自由をすべての人に」訴訟において5つの高裁すべてが違憲判決を言い渡したことを受けて一刻も早い法整備への着手を求める会長声明
-
- 2025(令和7)年3月7日に名古屋高裁が、同月25日に大阪高裁が、同性カップル※の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(以下「本件諸規定」という。)が憲法14条1項及び24条2項に違反するとの判断を示した。
これで、「結婚の自由をすべての人に」訴訟が係属している、札幌、東京、福岡、名古屋及び大阪の5つの高裁すべてにおいて、違憲判決が言い渡されたことになる。 - 名古屋高裁は、本件諸規定は、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠く性的指向による法的な差別取扱いであって、憲法14条1項に違反し、国会に与えられた立法裁量の範囲を超えるものとして憲法24条2項にも違反すると解するのが相当と判断した。
また、大阪高裁は、本件諸規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするものとして法の下の平等の原則に反するから、国会の立法の裁量の範囲を超えるものであって、憲法14条1項及び24条2項に違反すると解するのが相当と判断した。
他方で、両高裁は、同性婚を法制化しないことが憲法14条1項及び24条2項に違反することが国会にとって明白であるとか、国会が正当な理由なく長期にわたって法制化を怠っていたということはできないから、国家賠償法上違法とはいえず、賠償請求を棄却した原判決が相当であるとして本件控訴を棄却した。 - 名古屋高裁判決は、遺言や契約等の法律行為等により、婚姻によって付与される効果を一定程度実現できるとの国の主張に対し、法律婚制度には、両者の人的結合関係が法的に保護され、公証されることによって安定的で充実した社会生活を送る基盤となるという個人の尊厳と結び付いた本質的価値があるとし、当該本質的価値は法律行為等では実現できないことを明らかにした。
また、婚姻の本質は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるとして、婚姻の本質や目的を正しく捉え、このような永続性をもった生活共同体を形成することは、同性カップルにおいても成し得るものと指摘した。
そのうえで、同性カップルが法律婚制度を利用することができるようになった場合の弊害を、嫡出推定規定、戸籍制度及び社会保障法等との関係で詳細に検討した上、具体的な弊害が生じるとは言い難いと結論付けている。特に、戸籍制度に重大な変更をもたらすものではなく、法改正にあたり、膨大な立法作業が必要になるとは言えないとした点は、国会が直ちに法改正を行うことが可能であり、かつ、すべきであることを指摘したものとして高く評価すべきものである。 - 大阪高裁判決は、同性カップルの法的保護を法律上の婚姻と異なる形式で行うことは、法の下の平等の原則に悖るものといわざるを得ないし、新たな差別を生み出すとの危惧が拭えないとし、同性カップルについて法律婚以外の制度を設けたとしても、現時点において異性カップルと同性カップルの間に生じている不合理な差別を根本的に解消し得ないというべきとした。
大阪高裁判決が、別制度の制定では憲法14条1項違反の状態は解消せず、むしろ新たな差別を生み出すという弊害すらあり得ることまで指摘したことは、これまでの同種訴訟の判決にはない真の婚姻の平等を希求したものとして高く評価すべきものである。 - 今や、5つの高裁すべてが違憲判断をなす異例の事態である。
このことは、本件諸規定が違憲であることは司法の常識となったことを示すとともに、立法府が何らの立法措置を講ずる様子がないことに対する司法からの強い警告と受け止めるべきである。
にもかかわらず、林芳正官房長官は、大阪高裁判決直後の2025(令和7)年3月25日、「これまで出た4高裁の違憲判決は最高裁に上告されており、その判断も注視したい」と述べ、政府としては最高裁の判断まで何らの措置もとらないかのような姿勢を見せた。
この間にも、同性カップルは異性カップルであれば当然に享受できる法的利益を享受できないということだけでなく、それによって、社会的に存在を否定され、今この時もその尊厳を傷つけられ続けているのであるから、もはや注視をしている段階ではない。名古屋高裁が指摘するように、同性カップルが法律婚制度を利用することができるようになっても、具体的な弊害が生じるとは言い難く、法改正にあたり、膨大な立法作業が必要になるとは言えないことに加え、大阪高裁の指摘するとおり、なすべき立法の内容は、異性カップルと同じ婚姻制度を同性カップルにも適用するという内容のみなのであるから、直ちに法改正に着手するべきであるし、それは容易なことであるはずである。 - これまで当会は、2021(令和3)年から3度にわたって、同趣旨の声明を発出してきた。また、他の弁護士会あるいは日弁連においても同種の声明が繰り返し出されている。この違憲状態を速やかに解消すべき状況にあることは明らかである。
改めて、当会は、国に対し、5つの高裁すべてにおいて違憲判決が言い渡された現状を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、同性カップルにも異性カップルと同じ婚姻制度の利用を認める立法(法改正)に、一刻も早く着手することをなお一層強く求める。
※ 法律上または戸籍上割り当てられた性別において同性となるカップルの中には、同性愛者だけでなく、異性愛者のカップルもいる。例えば、生まれたときに割り当てられた性別は女性であるが、性自認は男性であるトランスジェンダー男性が、性別に違和を感じない女性(シスジェンダー女性)との結婚を望んだ場合、当該トランスジェンダー男性は異性愛者である。しかし、当事者の認識において異性カップルであっても、戸籍上同性となるため、法律婚をすることができない。したがって、法律上の同性カップルが結婚できないという問題は、同性愛者だけではなく、トランスジェンダーにも生じる問題である。以下、法律上同性となるカップルを「同性カップル」、法律上異性となるカップルを「異性カップル」という。
- 2025(令和7)年3月7日に名古屋高裁が、同月25日に大阪高裁が、同性カップル※の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(以下「本件諸規定」という。)が憲法14条1項及び24条2項に違反するとの判断を示した。
以上
2025(令和7)年4月17日
札幌弁護士会
会長 岸田 洋輔