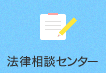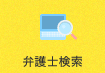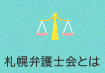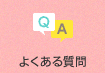地方消費者行政に対する財政措置の継続・拡充を求める意見書
第1 意見の趣旨
-
消費者が全国どこにいても消費者問題専門家による消費生活相談を受けられる体制の維持・整備を図るため、国は、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限を相当期間延長するか、少なくとも、同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置するべきである。
-
PIO-NET1(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録する事務、重大事故情報の通知事務、悪質業者・違反業者に対する行政処分を行う事務、適格消費者団体の活動支援事務などに対しては、国による恒久的な財政措置を講じるべきである。
第2 理由
-
意見の趣旨第1項について
2009(平成21)年の消費者庁創設以降、15年間に渡り、地方消費者行政の推進・強化のため、国から地方公共団体に対して交付金2 が交付されてきたが、2024(令和6)年から2025(令和7)年に、多くの地方自治体で地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付の期限を迎え、このままではその交付が終了する。
同交付金は、消費生活相談員の人件費に充てることができるものもあるなど、多くの地方自治体で消費生活相談体制の強化や消費者行政推進のための様々な事業に活用されてきた。消費生活相談員は、消費生活相談窓口において消費者からの相談にいち早く対応して、助言をし、消費者と事業者との間に入ってあっせんを行うなど、拡大を続ける消費者被害の救済に極めて重要な役割を担っている。交付金の終了は、消費生活相談員の人材確保にも支障を来すおそれがあり、かかる重要な役割を担う消費生活相談窓口の後退・縮小に直結しかねない。また、交付金は、他にも相談員の研修や、消費者教育・消費者啓発等にも活用されているところ、こうした事業の実施が困難になることも予想される。
そもそも、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金は、期限を設け、消費者行政予算における自主財源を増加させるための呼び水として設けられた。しかしながら、今日に至るまで自主財源による運営体制への移行は不十分であり、特に、小規模自治体の多くは交付金に依存している。
2024(令和6)年版の消費者白書によると、2023(令和5)年の全国の消費生活相談件数は約90.9万件、同年の消費者被害・トラブル推計額は約8.8兆円に及び、前年より2兆円以上も増額しているが、同交付金の終了により、消費者被害・トラブルに地方自治体が適切に対応できなくなる可能性が高い。
よって、全ての地方自治体が自主財源によって消費生活相談の十分な体制を維持・整備できるようになるまでの期間、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限を延長すべきであり、少なくとも同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきである。 -
意見の趣旨第2項について
現在、地域で発生する消費者被害の防止・救済の事務は基本的に自治事務とされている。
しかしながら、地方公共団体が行う消費者行政のうち、消費生活相談情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録する事務、重大事故情報の通知事務、悪質業者・違反業者に対する行政処分を行う事務、適格消費者団体の活動支援事務などは、それらによって得られた情報が国の行う立法政策や法執行・情報提供の根拠とされるなど、純粋に地方自治体のためだけの事務ではなく、国が行う消費者行政にもつながっており必要不可欠なものとなっている。こうした事務に関する費用(人件費や維持管理費用を含む)については、国の恒久的な財政措置を講じるべきである。
よって、立法的には、地方財政法10条3 を改正し、同条の列挙事項に上記のような国の事務の性質を有する消費者行政に関する経費を 加えるべきである。
2025(令和7)年4月25日
札幌弁護士会
会長 岸田洋輔
1 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報(消費生活相談情報)の収集を行っているシステムである。「行政機関による消費者被害の未然防止・拡大防止のための、法執行への活用」、「国・地方公共団体の消費者施策の企画・立案」も、目的に掲げられている。
2 2009年度から地方消費者行政活性化交付金、2012年度から地方消費者行政推進交付金、2018年度から現行の地方消費者行政強化交付金
3 地方財政法10条 「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期すためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。」とされ、「一 義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費」など、具体的な経費が35号まで列挙されている。