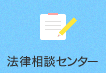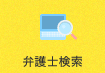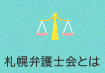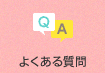憲法記念日にあたっての会長声明
本日、憲法記念日を迎えました。今年は、日本国憲法が施行されて78年になります。
日本国憲法は、一人ひとりがかけがえのない存在であるという「個人の尊厳」を最も重要な価値とし、それを堅持し、発展させるために、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を人類普遍の原理としています。これらは、将来にわたって護り続けていくべき尊い理念であるとともに、今私たちが直面している様々な課題への指針を示してくれるものでもあります。
2025(令和7)年は、1945(昭和20)年のアジア太平洋戦争の敗戦から80年目となります。日本国憲法は、先の戦争で国内外に多くの犠牲者を生じさせたことに対する深い反省に基づいて制定されたものです。それゆえ、日本国憲法は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」(前文)、「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(第9条)と規定し、徹底した恒久平和主義に立脚しているのです。
本年はまた、1945(昭和20)年8月6日の広島への原爆投下、同9日の長崎への原爆投下から80年が経過する年になります。昨年には、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。これは、「核兵器のない世界の実現を目指して尽力し、核兵器が二度と使われてはならないことを目撃証言を通じて身をもって示してきた」ことが高く評価されたものです。
しかし、現在でもなお、世界には1万2000発を超える核兵器が存在し、配備済み核弾頭だけでも3900発以上に上ります。核兵器保有国は、「核兵器を保有することで、戦争を防ぐことができる」という「核抑止論」に立ち、核兵器を手放そうとはしません。そして日本も、唯一の戦争被爆国でありながら、核の脅威に対しては米国の「拡大核抑止」、「核の傘」が不可欠との防衛政策をとっています。日本政府は、「核廃絶決議」を毎年国連に提出し、国として「核兵器のない世界の実現」を掲げているにもかかわらず、2017(平成29)年に国連で採択された核兵器禁止条約を批准しないばかりか、オブザーバー参加すらしていないのです。
しかし、そもそも「核抑止論」は、「自国が核を保有していれば、相手国はこの核による報復を恐れて攻撃を仕掛けることはできないであろう」という、相手国の戦争回避行動を期待する理論であって、その実効性にはなんらの確証もありません。そして、その理論が破綻しないという保証はどこにもなく、もしひとたびその理論が破綻すれば、世界を破滅させる核戦争に至るのです。現に、ロシアがウクライナへの核使用をほのめかして世界中を恐怖に陥れており、核兵器使用の危険性が現実化しています。国際社会において、「核兵器は使用してはならず、削減・廃絶しなければならない」ことはもはや否定しえないものとなっていますが、核抑止論に依拠している限り核兵器保有を認めることになり、このままでは核廃絶はなし得ません。
日本は、核兵器による被害の大きさ、悲惨さを身をもって体験している唯一の戦争被爆国として、核抑止論に依拠することなく、核廃絶に向けた行動を積極的に行わなければなりません。特に、核抑止論は「核兵器という武力による脅し」を正当化する議論であり、「武力による威嚇」を否定している日本国憲法第9条の理念に反し、また、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との日本国憲法前文の精神に真っ向から反するものです。
日本弁護士連合会では、これまで、第1回定期総会(1950年)における平和宣言をはじめとして、「今こそ核兵器の廃絶を求める宣言」(2010年)、「『核兵器禁止条約』の発効を歓迎する会長声明」(2021年)など、平和と人権の擁護、核廃絶に向けた、総会・人権擁護大会における宣言決議や会長声明を重ねてきました。
当会は、78回目の憲法記念日にあたり、日本国憲法の価値を改めて確認し、政府が日本国憲法の恒久平和主義の理念に基づき、外交と対話による安全保障を追求し、特に核兵器廃絶に向けた積極的役割を担うよう強く求めるとともに、核兵器廃絶に向けて、市民のみなさんと共に行動していくことを強く決意するものです。
2025(令和7)年5月3日
札幌弁護士会
会長 岸田 洋輔