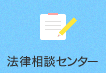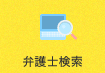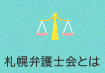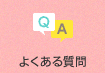今国会での再審法改正の実現を求める会長声明
- 静岡地裁は、昨年9月26日、「袴田事件」について、袴田巖さんに対し、再審無罪判決を言い渡し、同判決は確定した。袴田巖さんの身体拘束は、死刑囚として世界最長の約48年にも及んでおり、釈放された現在もなお、心身の回復には至っていない。
袴田事件において、警察・検察官の手持ち証拠の開示が実現したのは、事件から約30年も経過した後であり、2014(平成26)年3月27日に静岡地裁で再審開始決定が出されてから、さらに約10年を経過して、ようやく無罪判決が確定したものである。 - この間に、えん罪被害者を救済するための再審法改正を求める超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が立ち上がった。そして、本年3月25日の議連総会では、①再審手続における証拠開示に関する規定の整備、②再審請求審における検察官の不服申立て禁止、③通常審に関わった裁判官の除斥・忌避、④再審手続に関する規律の4項目を柱とする改正法の要綱案を承認する手続が取られ、現在、国会への改正法上程の準備が進められている。上記超党派議連が、再審における国選弁護制度の創設や再審請求中の刑の執行停止など他にも多数の重要な課題があるなかで、改正項目をあえてこの4項目に絞ったのは、迅速な法改正を重視したからである。
一方で、法務大臣は、本年2月7日に行われた記者会見で、再審制度の見直しに向けた法改正の検討を法制審議会に諮問することを明らかにし、本年3月28日の法制審議会臨時総会において、再審手続に関する部会設置を定め、去る4月21日から部会での審議が始まったところである。しかし、一般に法制審議会での審議は、年単位の期間を要することが多く、喫緊の課題に対応できず、迅速な改正の妨げとなりかねない。上記4項目以外の改正については、現時点では法制審議会で審議を尽くさざるを得ないとしても、法制審議会での審議が、上記4項目の迅速な改正の妨げとなるようなことは決してあってはならない。 - 袴田巖さんの無罪判決の確定後、「福井女子中学生殺人事件」では再審開始決定が確定し、現在再審公判が開かれているほか、「大崎事件」における第4次再審請求の特別抗告棄却決定における宇賀克也裁判官の反対意見、「鶴見事件」第3次再審請求の特別抗告棄却決定、さらには「姫路郵便局強盗事件」第2次再審請求の申立てなど、再審事件を巡る大きな動きが続き、法改正への機運がかつてなく高まっている。
これら多くの事件において、再審手続が異常なまでに長期化し当事者の高齢化を招いているのは、証拠開示規定の不備による証拠開示の遅延や不十分さと再審請求審における検察官の不服申立てに大きな要因があり、上記4項目の法改正の必要性は、もはや議論の余地がないほど立法事実としても明らかになっている。 - 日本弁護士連合会、北海道弁護士会連合会、当会を含む全国の各弁護士会は、再審手続法(刑事訴訟法等)の早急な改正を求めて、様々な取組を継続的に行ってきた。北海道内の地方議会においても、北海道議会を含めて110もの議会が再審法改正を求める意見書を採択したほか、全国各地の関係団体や市民団体からの改正を求める声も高まっている。さらには、国会主導での迅速な法改正を求める報道も活発化している。袴田事件に象徴されるように、再審手続を申し立てても、何十年もの間、再審開始決定に至らない、無罪判決が確定しないという状況は、決して許されない人権侵害であり、法改正には一刻の猶予もない。
当会は、国会に対して、引き続き再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止を含む再審制度(再審法)の改正を今国会(第217回国会)で実現するよう求めるとともに、政府に対して、法制審議会での審議が迅速な法改正の妨げとなることなく、速やかに法改正を実現させることを求め、あらためて会長声明を発出する。
以 上
2025(令和7)年5月7日
札幌弁護士会 会長 岸田 洋輔