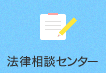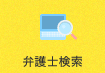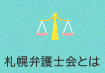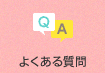いわゆる能動的サイバー防御法案の制定に反対する会長声明
本年2月7日、政府は、いわゆる「能動的サイバー防御法案」を国会に提出し、本年4月8日、衆議院は政府案に修正を加えた上で可決した。
本法案にいうサイバー攻撃とは、コンピューターシステム等に対し、ネット通信等を通じて不正に攻撃するものを指し、本法案は、「国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼす」おそれのある不正なサイバー攻撃の防止を図ることを目的とするものである。
本法案は、第1に、被害の防止を目的として、インターネット上の通信情報を政府が取得することを可能とし、第2に、不法なサイバー攻撃のおそれがある場合、攻撃者を検知し、攻撃元のサーバー等へ侵入して事前に無害化する措置(無害化措置)を執ることを可能としている。
しかしながら、これらの点については以下のような憲法上の重大な問題があり、適切な修正がされないのであれば、本法案を成立させることに強く反対する。
第1の点について、本法案では、通信情報の取得方法として、基幹インフラ業者(電気、ガス、石油、水道、鉄道、貨物自動車運転、外航海運、航空、空港、電気通信、放送、郵便、金融、クレジットカードの14業種、53企業、合計212社)との協定に基づいて提供を受ける方法、及び、国外が発受信となる通信情報については、協定や同意などがなくとも、独立機関(サイバー通信情報監理委員会)の承認を経て取得する方法が設けられている。
このうち、前者については、基幹インフラ業者との協定さえあれば、取得対象となる通信情報に制限が設けられていない。この点につき、本法案では、自動的な方法による機械的情報(すなわち、IPアドレスや指令情報等、意思疎通の本質的ではない情報)の選別を実施し、それ以外のものを直ちに消去することとされているが、漏洩等のおそれを排斥しえない。また、そのような機械的情報であっても、大量に収集・処理され、また、多種の情報と組み合わされた場合には、通信内容や個人の人格に関わる情報が推知されることもあり得るため、通信の秘密等に対する侵害となる可能性がある。さらには、いつ、誰が、誰に対して発信したか、という情報自体も通信の秘密(憲法21条2項後段)における重要な要素であるから、本法案による通信情報の取得は憲法21条2項後段に違反する疑いが強い。
また、後者の同意なき通信情報の取得については、その対象は国外が受発信となる情報(外外情報、外内情報、内外情報)に限られているが、国内相互の受発信となる情報(内内情報)であっても、海外のサーバーを経由した場合には国内通信とはならずに取得の対象となるため、同様の問題点がある。
このように、本法案は、国が、国民・市民に関する情報を広範囲で取得することを可能とするものであり、通信の秘密を害する危険性があるだけでなく、ひいては我が国の監視国家化をさらに進めることにもなりかねない。
次に、第2の点について、本法案は、無害化措置を執るため、警察官職務執行法及び自衛隊法等を改正し、警察官及び自衛官が、放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときに、①攻撃関係サーバー等の管理者等への措置の命令や、②攻撃関係サーバー等への措置(攻撃のためのプログラムの停止・削除等)を自ら実施できることを定めている。
このような無害化措置は、日本の警察官らが国外のコンピューターサーバーに無断でアクセスしてサイバー攻撃を行うことを定めるものであり、その対象が外国のものである場合には他国の主権を侵害することにもなりかねず、そのような措置を警察や自衛隊が独自の判断で行って良いのかも含め、より慎重な議論が必要である。
また、実際に本法案を所管するのが警察及び自衛隊ということになれば、収集された膨大な個人情報に警察、自衛隊らが自由にアクセスできることになるという懸念が生じ、法的にも強い疑問が残る。さらに、本法案では、集約された情報の整理・分析を政令で定める法人に委託することも予定されており、個人の通信やプライバシー情報が複数の機関に共有され管理されることになるが、その不正防止の歯止めのための措置が十分とは言えない。この点、サイバー通信情報監理委員会の設置の定めはあるものの、同委員会は行政権から独立しておらず、情報取得の審査の場面を除く他の場面(情報の処理・分析、提供・共有、保存・廃棄)における監視の権限についても明確に定められていない。
我が国では、サイバー攻撃対策として、不正アクセス行為禁止法、刑法改正、電子計算機損壊等業務妨害罪の強化、さらにはサイバー犯罪条約への採択など、すでに、諸外国との協力の下で一定の立法がなされている。現在までの国会審議では、これらの既存の立法では何が不十分なのか、なぜ本法案のような憲法上保障されている通信の秘密やプライバシー権という重要な諸権利を侵害しかねない法制度を設けなければならないのかが明らかにされているとは言い難い。
以上の理由から、当会としては、参議院において十分な審議・修正が行われないまま本法案を成立させることについて、強く反対するものである。
2025(令和7)年5月15日
札幌弁護士会 会長 岸田 洋輔