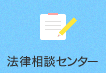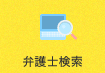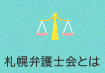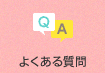日本学術会議法改正案に反対するとともに、日本学術会議の独立性と自律性の尊重を徹底することを強く求める会長声明
政府は、本年3月7日、国の特別機関とされている現在の日本学術会議(以下「学術会議」という)を廃止し、新たな特殊法人としての「日本学術会議」(以下「新法人」という)を新設する日本学術会議法案(以下「本法案」という)を閣議決定の上、国会に提出し、この法案は衆議院を通過した。
しかし、本法案は、学術会議の自律性、独立性を侵害するものであり、当会は本法案に強く反対する。
現行の日本学術会議法(以下「現行法」という)第3条は、学術会議の職務として、「独立して」科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ると規定し、学術会議の活動の独立性を定めている。この趣旨は、科学に関する審議においては、真理を探求するにあたり、学術会議が政治的権力や外部からの圧力を受けずに判断できることを担保することが何よりも重要であるため、その独立性を保障する点にある。このような独立性の確保は、戦前の滝川事件(1933年)や天皇機関説事件(1935年)において、学問研究が時の政府から弾圧され、真理探究が歪められたという歴史的反省に鑑みて、日本国憲法第23条が学問の自由を保障したことに由来する。
現行法前文では、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするとされており、このような理念の下に設置された学術会議は、我が国を代表するナショナル・アカデミーといえる。
先述の使命を有する学術会議がナショナル・アカデミーとしての役割を果たすためには、①学術的に国を代表する機関としての地位、②そのための公的資格の付与、③国家財政支出による安定した財政基盤、④活動面での政府からの独立、⑤会員選考における自主性・独立性、という5要件を具備することが必要である(2021年4月22日、学術会議が発表した「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」より。なお、これら5つの要件は、ナショナル・アカデミーとして備えるべき要件として国際的に広く共有されている。)。
他方、本法案では、第1条において「我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術に関する重要な審議(中略)等を行うことにより、学術の向上発展を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与すことを目的とする」と定められ、あたかも新法人がナショナル・アカデミーであるかのような位置付けがされている。
しかしながら、本法案では、現行法第3条の「学術会議は独立して(中略)職務を行う」との文言が踏襲されておらず、ナショナル・アカデミーたりうる根幹としての独立性が大きく損なわれていることに加え、以下のとおり、会員の選考、活動、財政基盤のいずれの点においても、新法人の自主性・独立性が脅かされる内容になっている。
会員の選定については、新法人の会員以外の者で構成される「選定助言委員会」という組織を新たに設け、同委員会が新たな会員の選定方針の作成等に意見を述べるものとされている(本法案第26条)。そうすると、選定方針の作成を通じて新法人の外部から会員の選定自体に影響を及ぼすことが可能となり、会員選考における自主性・独立性が脅かされることとなる。
学術会議での会員選考については、これまで学術会議において推薦した学識経験者を政府が任命していたが、2020年9月には政府が理由も示さずその任命を拒否した先例がある。この任命拒否は、時の政権にとって都合の悪い者を会員とすることを拒むという恣意的な運用であると批判されてきたが、本法案はむしろそのような恣意的な会員選考を可能とするものである。
また、活動面については、会員以外の者で構成される運営助言委員会による活動計画の作成や予算の作成、組織の管理・運営への関与(同第27条)、内閣総理大臣が任命する「評価委員会」への自己評価報告書の提出(同第42条第3項、第51条)、内閣総理大臣が任命する「監事」による監査(同第19条、第23条)が行われるものと規定されている。これらの規定は現行法には存在せず、新法人が外部の意向に従って活動することを制度として導入するものといえる。このような制度は、新法人の活動内容そのものの独立性を否定し、外部、特に政府からの監視、関与、介入という圧力を加えることを可能とするものであって、その独立性を侵害するものである。
さらに、その財政基盤に関し、本法案では、政府は新法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の「全部又は一部に相当する金額」を補助することができる、と規定されている。これはすなわち、新法人への財政支援が必要な財源の一部にとどまることもあり得ることを意味し、現行法が学術会議の経費を国庫負担とするとして(現行法第1条第3項)、その独立性を保障していたことを正面から否定するものである。
そして、本法案に先行して発表された2023年12月11日付内閣府特命担当大臣決定「日本学術会議の法人化に向けて」及び2024年12月20日付「世界最高のナショナル・アカデミーを目指して~日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会最終報告書~」において、学術会議について「財政基盤の多様化」や「外部資金の獲得」等が繰り返し求められていることをも踏まえると、新法人が、政府の財政支援を失うことを避けるために、あるいは産業界等から外部資金を獲得するために、政府あるいは産業界の意向に従属的にならざるを得なくなることが深刻に危惧される。
さらに、本法案によれば、前述した現行法の前文が削除されることになるが、これは新法人が学術会議の設立趣旨とその使命を踏襲しないことを意味し、これまでの学術会議の在り方を真っ向から否定するものにほかならない。
当会は、学術会議の独立性と自律性を奪い、我が国の研究者の学問・研究の自由を脅かすこととなりうる本法案に強く反対するとともに、学術会議の独立性と自律性の尊重を徹底することを強く求めるものである。
2025(令和7)年5月19日
札幌弁護士会 会長 岸田 洋輔