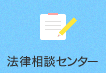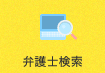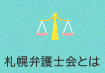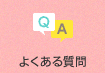死刑執行に抗議する会長声明
- 2025(令和7)年6月27日、東京拘置所において確定死刑囚1名の死刑が執行された。2022(令和4)年7月26日に1名の死刑が執行されて以来の執行であり、石破内閣発足後及び鈴木馨祐法務大臣就任後、初めて死刑が執行されたことになる。
- 死刑は国家が人の生命を奪うという究極の刑罰である。本年6月には、懲役刑と禁固刑を統合して拘禁刑に再編する改正刑法が施行されたが、これは、応報から更正と教育を主眼とする刑罰制度への移行を意味するものである。しかし、死刑は、更正を目的としない唯一の刑罰であり、拘禁刑の理念とは決して相容れない。
また、死刑制度には犯罪抑止効果があるなどとして、死刑制度の存置について賛成する意見があるものの、他方で、死刑については他の刑罰と比較して特別な犯罪抑止効果があるという科学的な証明がなされておらず、死刑制度の存廃については、必ずしも国民の間で十分な議論がなされたり、見解の一致を見ているとは言い難い状況にある。
さらに、刑事裁判という手続で人が判断する以上、常に誤判やえん罪の危険を伴うところ、誤って死刑が執行された場合には、事後的に回復を図ることは不可能である。昨年の袴田事件再審無罪判決は、戦後5件目の「死刑台からの生還」であったが、刑事裁判に誤判やえん罪が生じ得ることは、これまでの多くの再審無罪判決が明らかにしている。 - 国際社会の潮流は、死刑廃止に向かっており、国際連合の自由権規約委員会は、日本の第6回定期報告に対する最終見解(2014年7月23日採択)において、死刑判決に対する必要的な上訴制度がないこと、再審請求に死刑の執行停止効がないことなど、日本の死刑制度には国際人権基準の観点から問題があると指摘し、日本政府に対してその改善を求めると共に、死刑の廃止を目指し、規約の第二選択議定書(死刑廃止選択議定書)への加入を求めている。
また、2018(平成30)年12月17日には、国連総会において、死刑の廃止を視野に入れた死刑の執行停止を求める7回目の決議が、これまでの最多の121か国の賛成により採択された。
さらに、2024(令和6)年の時点で死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない事実上の廃止国を含む。)は145か国にのぼり、世界の3分の2以上の国において、現在、死刑の執行はなされていない。 - 国内においても、2024(令和6)年2月29日には、国会議員や法律学者、法律実務家に加え、被害者団体や労働団体、報道機関などの有識者が参加して「日本の死刑制度について考える懇話会」が設置され、同年11月13日に報告書が公表された。報告書では、委員全員の一致で、現行の日本の死刑制度とその現在の運用の在り方は、放置することの許されない数多くの問題を伴っており、これを現状のまま存続させてはならないとし、早急に国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置するよう提言した。
- このような死刑制度が抱える重大な問題点や国際的な死刑廃止への潮流に呼応するように、日本弁護士連合会は、2016(平成28)年10月7日、第59回人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、2020(令和2)年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを宣言している。
また、当会は、2019(平成31)年2月26日に「死刑執行の停止及び死刑制度の廃止を求める決議」を臨時総会において採択し、国に対し、死刑確定者に対する死刑の執行を直ちに停止し、速やかに死刑制度を廃止することを求めたほか、これまでも死刑が執行される度に、政府に対し、強く抗議をするべく会長声明を発出してきた。 - 今回の死刑執行は、このような死刑制度を巡る国内外の情勢の変化や、これに伴う死刑制度の廃止に向けた動きをことごとく無視するものであって、極めて遺憾であると言わざるを得ない。
当会は、政府に対し、今回の死刑執行に対して強く抗議するとともに、死刑の執行を直ちに停止のうえ速やかに死刑制度を廃止するよう求める。
以上
2025年7月1日
札幌弁護士会
会長 岸田 洋輔