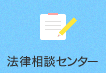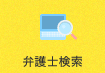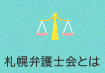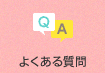最高裁判所が生活扶助基準の引下げを違法と判断したことを高く評価し、生活保護利用者及び元利用者への謝罪及び補償、違法な引下げがなされた原因の調査、検証の実施並びに今後の生活保護基準の改定の適正化を求める会長声明
- 2025年6月27日、最高裁判所第三小法廷は、大阪府内及び愛知県内の生活保護利用者らが、2013年8月から3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)に係る生活保護費減額処分の取消し等を求めた各訴訟の上告審において、いずれについても厚生労働大臣による本引下げの違法性を認め、生活保護費の減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
- 本引下げは、生活扶助基準額と低所得世帯の消費実態との乖離を調整することを名目とした「ゆがみ調整」及び2008年から2011年までの「物価下落」を名目として改定前の基準生活費を一律に-4.78%減じた「デフレ調整」の二点を理由として、生活保護利用世帯の生活扶助基準額を平均6.5%、最大10%引き下げたものであった。
本判決は、このうちデフレ調整について、生活扶助の老齢加算廃止の判断が争われた2012年2月28日及び同年4月2日の各最高裁判決で示された「判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査される」との判断枠組みに照らし、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間の「不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議検討が経られていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められ」ず、「デフレ調整における改定率の設定については、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱、濫用があり、本引下げは生活保護法3条、8条2項に違反して違法と判断した。 - 本判決は、厚生労働大臣によって行われた生活保護基準の改定自体を違法と判断した初めての最高裁判所判決であり、厚生労働大臣が「個人の尊重」(憲法13条)の基盤となる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、生活保護法3条)の重要性を軽視し、生活保護法8条2項によって考慮すべき事項を考慮せずに行った本引下げを違法と断じた上、この違法な引下げに基づく保護費減額処分の取消しを認めたものであり、最高裁判所が司法としての役割を果たしたものとして高く評価できる。
- 国は、本判決を受け、本引下げが行われた期間に生活保護を利用していた数百万人の生活保護利用者らの「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」という極めて重要な権利を侵害した事態を深刻に受け止め、現在も全国の裁判所に係属している同種訴訟について全面解決を図り、提訴した者らを含むすべての生活保護利用者及び元利用者に対して謝罪をするとともに、本引下げ前の基準によって受けるべきであった生活扶助費と実際の支給額との差額を支給するなど全面的な補償措置を直ちに講じるべきである。
この点、厚生労働大臣は、本判決を受け、2025年7月1日の記者会見において、「判決の趣旨及び内容を踏まえた対応の在り方について、早期に、専門家によりご審議をいただく場を設けるべく、検討を進めていきたい」旨を表明したが、その審議や検討は、本判決の内容を踏まえ、原告らを含むすべての生活保護利用者及び元利用者に対する完全かつ速やかな補償の実現を前提とするものでなければならない。 - さらに、国においては、違法な生活扶助基準の引下げが再び行われることのないよう、本引下げが行われるに至った具体的な事実経過や原因等について、徹底的な調査及び検証が実施されるべきである。
そして、今後、国が生活保護基準を改定するにあたっては、①生活保護基準部会等の検証を経ることをルール化すること、②生活保護基準部会の委員に生活保護の利用当事者や弁護士、支援者を選任すること、③生活保護基準の低さの根本的な原因となっている低所得層(第1・十分位等)との比較によらない新たな検証手法(例えば、最低生活に必要な需要を積み上げる方法等)を採用することにより、その改定が適正に行われることも必須である。 - なお、本判決においては、デフレ調整が違法であるだけでなく、2分の1処理(ゆがみ調整において、生活保護基準部会による検証結果を2分の1のみ反映させたこと)の判断過程にも過誤があり、ゆがみ調整とデフレ調整の併用も違法であるとして、国家賠償請求についても認容されるべきであるとした宇賀克也裁判官の反対意見も示されている。
この反対意見の中では、多数意見が言及していない本引下げに係る種々の問題点も的確に指摘されており、特に原告らが「『最低限度の生活の需要を満たす』ことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえ」ないと指摘した部分は、まさに本引下げに対して長年訴訟でたたかってきた原告らの思いを汲んだものといえ、重く受け止められるべきである。 - 以上より、当会は、最高裁判所が本引下げを違法と判断したことを高く評価し、国に対し、本判決を踏まえた生活保護の利用者及び元利用者への謝罪及び全面的な補償措置を直ちに実施するよう求めるとともに、違法な生活保護基準の引下げが再び行われることのないよう、本引下げがなされた具体的な事実経過や原因等の調査、検証及び今後の生活保護基準の改定の適正化を強く求める。
以 上
2025年7月15日
札幌弁護士会
会長 岸 田 洋 輔