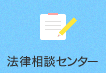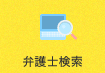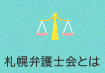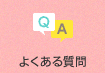「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決の確定を受けて、捜査機関に対し、真摯な謝罪と再発防止のための検証を求めるとともに、国に対しては、今後のえん罪被害を防止するため、本事件に関する検証並びに取調べの全面可視化等の抜本的改革及び再審法の可及的速やかな改正を求める会長声明
- 本年7月18日、名古屋高裁金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」の再審公判において、前川彰司氏に対し、再審無罪判決(検察官控訴の棄却判決)を言い渡し、8月1日、同判決は検察官による上訴権放棄により確定した。
同事件は、1986年3月19日に、福井市内の市営団地で女子中学生(当時15歳)が何者かに殺害された事件である。事件発生から約1年後、捜査機関は、客観的な証拠がない中で、犯行後の前川氏を目撃したとする関係者らの供述をもとに、当時21歳であった前川氏を逮捕、起訴したが、前川氏は一貫して犯行を否認していた。
確定審第一審(福井地裁)は、変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定して無罪判決を言い渡したが、確定審控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、一転して供述の信用性を認め、一審判決を覆して有罪判決(懲役7年)を言い渡し、同判決は最高裁で確定した。
前川氏が2004年に申し立てた第1次再審請求では、請求審(名古屋高裁金沢支部)において関係者らの供述調書など95点の証拠が新たに開示され、2011年に再審開始が決定された。しかし、検察官の異議申立てを受けた異議審(名古屋高裁)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして再審開始決定を取り消し、特別抗告審もこの判断を是認した。
2022年、前川氏は、第2次再審請求を申し立てた。請求審(名古屋高裁金沢支部)では、裁判所の積極的な訴訟指揮により、287点もの証拠が新たに開示され、その中には、関係者の供述の信用性を左右する極めて重要な証拠も含まれていた。昨年10月23日、請求審は、新旧証拠の総合評価を行った上、関係者の一人が自己の利益を図るために前川氏を犯人とする虚偽供述を行い、捜査機関が他の関係者に誘導等の不当な働きかけを行って関係者らの供述が形成されていった具体的かつ合理的な疑いがあるとして、関係者らの供述の信用性を改めて否定し、再審開始を決定した。その後、検察官が異議申立てを断念し、この再審開始決定が確定した。
本判決は、上記2度目の再審開始決定を受けた再審公判における無罪判決である。通算して4度目の無罪判断であり、事件から前川氏の雪冤が果たされるまでに約39年もの歳月を要したということになる。 - 本判決は、捜査に行き詰まった捜査機関において、前川氏が犯人であると証言した主要関係者の一人に対し、供述を引き出すために、取調室での親族との面会や親族による飲食物の差し入れを許すなどの不当な利益を供与した上、同人と他の主要関係者を面会させたり、供述内容を示唆して誘導するといった他の主要関係者に対する不当な働きかけを行い、その結果、同人の供述に沿う主要関係者供述が形成されていった具体的かつ合理的な疑いが残るとし、確定審控訴審が有罪判決の根拠とした関係者供述の信用性を否定した。
また、確定審検察官が、裏付け捜査の結果、関係者の供述が客観的真実に反していることを知りながら真実に反する主張を続けたことに関し、「被告人から正しい事実関係を前提とした主張・立証の機会を奪い、裁判所にも動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま有罪判決をさせるなど、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったといわれても仕方がない訴訟活動に及んで」おり、「確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられるのであって」「公益の代表者としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ない」とまで判示した。これは、湖東記念病院事件の再審無罪判決において、「取調べや客観証拠の検討、証拠開示のどれか一つでも適切に行われていれば、このようなことにはならなかった」と裁判長が触れたことと重なる指摘である。
本判決が指摘するとおり、検察、警察の不正、不当な活動ないしその具体的な疑いは、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものである。
当会は、捜査機関の不当な捜査手法や公判活動を厳しく糾弾し、前川氏の無罪を高らかに宣言した本判決を高く評価する。 - 本判決において、検察側の証拠隠しが認定されたことに関し、名古屋高検の次席検事は、「不公正だと評価されたのは当然」「検察としても真摯に反省し、教訓とすべき」としつつも、前川氏への謝罪や経緯の検証については「特別なことは行わない」と断言した。また、福井県警の本部長も、前川氏への謝罪や検証について明言を避けた。
裁判所から、これほどまでに捜査手法や公判活動の在り方を厳しく批判されたにもかかわらず、組織としての謝罪もせず、進んで検証を行うこともしないということは、組織としての自浄能力の欠如に加え、基本的人権の軽視、遵法精神の欠如という捜査機関の悪しき体質の根深さを顕著に現しているというほかなく、市民の理解や信頼を得ることなど到底できない。
昨年9月に「3つのねつ造」が認定された袴田えん罪事件の無罪判決確定以降も、湖東記念病院事件や大川原化工機事件の各国賠訴訟において、捜査機関による違法な取調べや事件自体の虚構性が裁判所によって認定され、原告勝訴判決が出されている。大川原化工機事件においては、捜査員が、故意を否認する元取締役に対して偽計的な説明をして重要な弁解を封じた上、犯罪事実を認めるかのような供述に誘導したことは違法の評価を免れないと指摘されている。
このような供述の誘導や威迫による違法・不当な取調べは、現在でも実際に行われているのであり、捜査機関の違法体質は、今も昔も何ら変わっていない。判決後の名古屋高検及び福井県警の対応からすれば、捜査機関による検証のみでは足りず、刑事弁護人や刑事法学者、元裁判官らによって構成される第三者機関を立ち上げるなどし、捜査や公判活動の在り方について十分な検証を行う必要があるほか、全ての被疑者及び参考人の取調べの可視化及び弁護人の立会い制度の法制化等の抜本的な制度改革も不可欠である。 - 本件においては、前川氏の雪冤に39年もの歳月を要している。これほどまでに時間を要したのは、再審法の規定の不備によるところが大きい。
第1次再審請求における再審開始決定に対し、検察官による異議申立てがなければ、前川氏は早々に再審公判に臨むことができた。また、第2次再審請求審において開示された新証拠がもっと早く開示されていれば、有罪を基礎づけた関係者供述の信用性には、より早期の段階から疑義が呈されたはずである。
当会は、本年5月7日付で「今国会での再審法改正の実現を求める会長声明」を発出したところであるが、本判決により再審法の早期の改正の必要性がよりいっそう明らかとなった。 - よって、当会は、「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決の確定を受けて、捜査機関に対し、本事件に関する真摯な謝罪と再発防止に向けた適切な検証を求めるとともに、国に対しては、今後のえん罪被害を防止するため、本事件に関する検証並びに取調べの全面可視化や弁護人立会い制度の法制度化等の抜本的改革及び再審法の可及的速やかな改正を求める。
以 上
2025年8月26日
札幌弁護士会
会長 岸 田 洋 輔