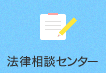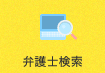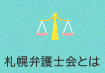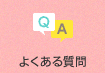骨太の方針2025を踏まえ、谷間世代を中心とする若手・中堅法曹のための基金制度の早期実現を求める会長声明
本年6月に策定された政府の「経済財政運営と改革の基本方針2025」(いわゆる「骨太の方針」2025)は、「骨太の方針」2024に続き、「法曹人材の確保等の人的・物的基盤の整備を進める」ことを方針に掲げ、さらに、「法曹人材の確保等」の注記には「法教育の推進、公益的活動を担う若手・中堅法曹の活動領域の拡大に向けた必要な支援の検討を含む」ものであると明記された。
これは、2017年(平成29年)4月、裁判所法の改正によって、同年11月1日以降に採用された司法修習生(第71期以降)に対しては基本給付金などの修習給付金が支給されることとなった一方、2011年(平成23年)11月から2017年(平成29年)10月までの間に採用された司法修習生(新65期~70期、いわゆる「谷間世代」)には新たな給付金制度の遡及適用がなかったために生じた、谷間世代が無給での修習によって重い経済的負担を強いられたまま取り残されるという不公平な問題の解決策として、日本弁護士連合会、全国の各弁護士会、各弁護士会連合会及び新たな給付金制度の実現に向けて積極的に活動してきた団体(ビギナーズ・ネット)を挙げて取り組んできた谷間世代に対する修習給付金と同額の一律給付による解決、また、実質的に谷間世代への一律給付と異ならないような基金制度の創設を目指してきたことが反映された結果である。
本来、法曹は、三権の一翼を担う司法という社会インフラの整備として公費により養成されなければならず、一時的に公費による養成が途絶えた状態は修復されるべきである。世代を問わず全ての法曹が公費により養成され、その公的役割を自覚し、十分に力を発揮することは、この国の司法制度を利用する全ての人の利益となる。司法制度の最終的な受益者は,その利用者である国民であり、司法制度を支える法曹は社会の人的インフラである。国には公費で法曹を養成する責務がある。
近年の大規模自然災害や多くの社会問題が発生する中で、弁護士の活躍の必要性は高まっており、この状況下で国民のための司法を維持及び強化するためには、早期に谷間世代の問題を解決することが必要である。
そこで、谷間世代の問題を解決すべく、当会も市民に幅広くこの問題をアピールするとともに、国会議員その他様々なルートを通じて活動してきた。そして、この問題の解決に向けて国会議員から寄せられたメッセージは2025年(令和7年)8月30日時点で375通に達した。これらのメッセージは正に国民の声であり、この問題の早期解決を求める意思の表れである。
さらに谷間世代の問題は司法の場でも指摘され、名古屋高等裁判所令和元年5月30日判決では、「従前の司法修習制度の下で給費制が果たした役割の重要性及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については、決して軽視されてはならない(中略)例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられるが、そのためには、相当の財政的負担が必要となり、これに対する国民的理解も得なければならないところであるから、その判断は立法府に委ねざるを得ない」とされている。正に立法府の判断が求められる状況にあるといえる。
このような状況下で、日本弁護士連合会は、今般、谷間世代への直接給付ではないものの、不公平な状態におかれて経済的負担を強いられた谷間世代等に対し、経済的な負担感や不公平感を軽減することを目的とし、谷間世代等の活動を幅広く支援するといった内容の基金制度の創設を提案した。これは実質的な一律給付に代わりうるものとして位置づけられる。
当会は日本弁護士連合会、全国の各弁護士会及び各弁護士会連合会とも力をあわせ、引き続き谷間世代問題の解決に向けて一層の尽力を重ねる決意であるが、政府、国会及び裁判所等の関係機関におかれては、「骨太の方針」2025及び日本弁護士連合会が提案する基金制度の目的に即して、早期の実現に向けて必要な措置を講じていただくよう強く求める。
2025年(令和7年)10月14日
札幌弁護士会
会長 岸田 洋輔