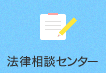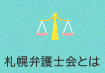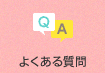中間利息控除の立法化に反対する会長声明
法務省は、法制審議会民法(債権関係)部会の決定に基づき、本年4月16日「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(以下、「中間試案」という。)を公示し、現在、期限を本年6月17日までとして中間試案に対する意見を公募している。
中間試案は、低金利の状況が長期にわたって続いている経済情勢の下では、現在の民事法定利率(以下、「法定利率」という。)年5パーセントは高すぎるとして、法定利率を年3パーセントに引き下げ、あわせて法定利率を固定制から変動制にすることを提案する一方、民法に明文規定がなく、判例に基づき年5パーセントの法定利率によって行われている中間利息控除について、「損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合には、それに用いる割合は、年[5パーセント]とするものとする。」として、年5パーセントの割合による中間利息控除の立法化を提案している。
しかしながら、中間試案における中間利息控除に関する提案には,次のとおり大きな問題がある。
損害賠償額算定における中間利息控除は、将来に現実化する損害について現在一時金で賠償を受ける被害者や受傷者(以下、「被害者等」という。)が、損害が現実化するまでの期間賠償金を運用できることになるから、公平の見地からこの間の運用益を予め控除するものである。一方、法定利率は、債権者が履行期に金銭を受領して運用したならば得られた運用益、または、履行期に受領できるはずの金銭を他から入手する調達コスト(借入金利)を債務者に負担させるものである。運用益の観点からすれば、中間試案の提案のごとく、なぜ被害者等が債権者となる場合にだけ運用益を高く見込むのか説明がつかない。また、調達コストの観点からは、銀行預金の利子(運用益)と銀行からの借入利息(調達コスト)との比較の例をあげるまでもなく、大多数の市民にとって調達コストに比べて運用益の方が低いにもかかわらず、中間試案における中間利息控除に関する提案では両者が逆転してしまうとの批判を免れない。
また、法定利率の割合により中間利息控除を行うことを明示した最高裁平成17年6月14日判決は、その理由について、法的安定及び統一的処理の必要から、「被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても」、「民法は、民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる」と判示している。これによれば、民法は、法定利率が変更された場合、あわせて中間利息控除の利率も変更されることを当然予定しているといえる。損害賠償額の算定に関してのみ変更前の法定利率年5パーセントの割合により中間利息控除を行うとの立法提案は、上記判例の趣旨に明らかに反する。
さらに、中間試案の提案では、被害者等にとって酷な結果を生じさせている現状を追認する結果となる。例えば、中間利息控除につき複利控除するライプニッツ方式を採用の上、労働能力を全て喪失した年収450万円の被害者等について、年5パーセントの割合で中間利息を控除して逸失利益を算出すると(以下、端数は四捨五入)、労働能力喪失期間が10年間では3475万円、20年間では5608万円、30年間では6918万円になる。ゼロ金利政策の経済情勢に鑑み、仮に運用益をゼロとすれば、上記の額は、結果として、労働能力喪失期間10年間では7.7年分、20年間では12.5年分、30年間では15.4年分のみしか認めないことを意味する。一方、同じ条件のもと年3パーセントの割合で中間利息を控除して逸失利益を算出すると、労働能力喪失期間10年間では3839万円(8.5年分)、20年間では6695万円(14.9年分)、30年間では8820万円(19.6年分)になる。このように年3パーセントの割合で中間利息を控除したとしても被害者等に対する賠償額は必ずしも十分とはいえないが、仮に、5パーセントの割合による中間利息控除を維持するとなれば、適正な損害賠償額から乖離している現状を追認する結果となる。
なお、中間試案の提案においては、法定利率が変動制になった場合に、将来長期にわたって控除する中間利息の利率を定め難いことが主な根拠とされているが、これは実務の運用によって克服可能な問題であり、変動制を理由に損害賠償の中間利息控除の利率のみを年5パーセントに温存するというのは説得的ではない。
以上の理由から、当会は、年5パーセントの利率で損害賠償額の中間利息控除を行うことを改正民法に明記して立法化することについて、強く反対する。
2013年5月14日
札幌弁護士会 会長 中村 隆