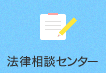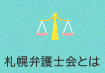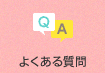家族法制の見直しに際し、離婚後双方親権を導入することに反対する意見書
第1 意見の趣旨
当会は、家族法制の見直しに際し、離婚後双方親権を導入することに強く反対する。
第2 意見の理由
-
法制審議会での議論状況
現在、法制審議会で家族法制の見直しが進められており、令和4年11月15日に「家族法制の見直しに関する中間試案」が取りまとめられたが、その後も家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けて議論が続けられている。
今回の議論において、最も注目されているのは、離婚後双方親権の導入についてである。現行法では、離婚をするときは、父母の一方を親権者と定めなければならないところ(民法819条1項2項)、離婚後双方親権が導入されると、離婚後も父母の双方を親権者と定めることができるようになる。法制審議会家族法制部会第32回会議(令和5年10月31日開催)議事速報によると、現在法制審議会では、離婚をするときは、その双方又は一方を親権者と定める方向で審議されているようである。 -
離婚後双方親権の重大な問題点
しかし、離婚後双方親権は、実現しても子の利益に資するところが乏しく、かえって子の利益を害する危険が大きい。また、父母の一方が他方に対し、離婚後双方親権を口実にして離婚後も接触を強要したり相手を支配する手段として利用することも懸念される。以下、具体的な問題点のうち重要なものを挙げる。(1) 子の重要事項に関する意思決定が停滞し子の利益を損なうおそれが極めて大きい
離婚後双方親権は、離婚後も継続して父母が養育に関わることが子の利益に 適うという理念から導入が主張される傾向にある。しかし、そのような理念は具体性がなく、むしろ現実から乖離している。なぜなら、離婚は父母間の信頼関係が失われたためになされることがほとんどであり、また離婚に至る過程で高葛藤に陥ることも多く、そのような場合養育のための協議すら困難となるため、子の重要事項に関する意思決定が停滞するばかりか、高葛藤によるストレスがかえって子の家庭環境を悪化させるからである。このような状態が子の利益に適っていないことは明らかである。しかも、高葛藤の父母間での協議を必要とすれば、関与の認め方によっては、別居親は拒否権を有することになり、相手を支配する手段として度々反対意見を述べることも懸念される。
子に関する意思決定が停滞した場合に裁判所がいずれの親権者の判断を採用すべきかを決するとする案も検討されているが、裁判所においてこのような判断を適時・適切に行うことは困難である。すなわち、裁判所は、そのパブリックコメント(以下「裁判所意見」という。)において、判断に緊急を要する場合であっても「当事者双方の主張立証ないし意見聴取に加え、審問や子の意向調査等があり得るとすると、裁判所の審理・判断には相応の期間を要し、調停手続の利用を前提とすればその期間も要するほか、不服申立ての手続も考慮すると、親権の行使が必要となる時期までに適切な審理を尽くすことができる制度となるかについては慎重な検討を要する」と実務上の観点から具体的な懸念を表明している。
また、子の養育方針についてはさまざまな価値観があり得るところ、裁判所意見は、父母のいずれの親権行使の在り方がより望ましいかといった価値判断の優劣を司法判断することは、国家による価値観の押しつけとなって相当でなく、かつ、困難である旨表明している。
さらに、DV(身体的暴力だけではなく、精神的・経済的・性的暴力も含む、以下同じ。)などによる父母間の支配・被支配の関係があった場合に離婚後も父母の協議を要するとすれば、父母間の支配・被支配の関係の継続につながり、それを実効的に防止することは、少なくとも現行の司法・行政のリソースでは困難である。(2) 裁判所が双方親権不適切ケースを全て除外できるわけではない
(1)で挙げた問題点に対し、離婚後双方親権の選択については父母間の協議や裁判所の関与によって不適切なケースは除外できるとする反論があるかもしれない。
しかし、父母間の協議では離婚を実現するなどのために一方が不本意な譲歩をして離婚後双方親権を受け入れる場合などが想定されるし、DVなどの証拠に表れにくい家庭内の問題を裁判所の限られた役割・リソースの下で見抜くことは困難である。
また、離婚紛争の長期化は避けられない。すなわち、裁判所意見が「父母の双方を親権者とするか一方を親権者とするかについて、要件該当性を判断し、次に、父母の一方を親権者とする場合には、父母のいずれかを親権者と定めるかを判断するという2段階の審理を要する上に、前者の争点を審理する段階では後者の争点について調査官調査を実施することができずに紛争が長期化するおそれがあり、こうした点も踏まえて要件の定め方を検討する必要がある」と指摘しているとおりである。(3) 親権の所在と監護の方法は別の問題である
離婚後双方親権の導入によって、離婚後の父母の共同監護が容易になると期待する向きもあるようである。しかし、子の監護の方法と親権の所在とは別の問題である。現行の制度の下でも、比較的良好な関係にある離婚した父母が共同監護を行うことは自由である。他方で、父母間の信頼関係が失われて離婚に至る多くの場合、仮に離婚後双方親権とされても、共同監護は全く現実的ではない。
また、離婚後双方親権の導入によって、面会交流が促進されると期待する向きもあるようである。しかし、別居親が親権者であろうがなかろうが、子の利益に資する限りで面会交流はこれまでも実施されてきたし、今後も同様であろう。現在の面会交流の運用について改善すべき点があるとしても、それは離婚後双方親権の導入とは別の問題である。
さらに、離婚後双方親権の導入によって、父母の一方が他方に無断で子連れで別居した場合に、別居親が子を連れ戻すことが可能になることを期待する向きもあるようである。しかし、これは監護者指定の問題であって、現行の制度の下でも審判前の保全処分などによって父母のいずれが監護者として相応しいかが裁判所によって判断されて解決されているし、今後も同様であろう。監護者の指定を含む子の監護の方法と親権の所在とは別の問題であることは、前述のとおりである。(4) 双方親権により養育費の支払が促進される根拠はない
離婚後双方親権の導入によって、別居親に自覚が生まれ、養育費の支払いが促進されることを期待する向きもあるようである。しかし、そのような精神的な変化が生じるとする実証的根拠はない。養育費の支払いの確保は、今回の家族法制の見直しの別の箇所で検討されているより実効性ある方策を推し進めることによるべきである。(なお、法制審議会家族法部会では、双方親権とした上で監護者の定めをおかない案も出されているが、それではそもそも主たる養育者が養育費やひとり親への手当を受け取れない事態が発生しかねず、問題である。)(5) 現行法下でも離婚後父母による共同監護は可能である
離婚後双方親権の導入によって問題が生じうるとしても、離婚後双方親権を望む者がいる以上、選択肢を設けた上で問題が生じる場合に認めなければよい、あるいは、双方親権を選択するための要件を定めればよい、との議論もある。しかし、離婚後双方親権という選択肢が設けられることによって、父母の協議の名のもとに離婚後双方親権を押し付けられる例が生じることは、父母間の支配・被支配関係がしばしばみられる現状にかんがみて容易に予想できる。また、離婚後双方親権を望む者が期待するメリットは、父母の関係が良好であれば現行の制度のもとでも協議によって実現できるものである。(6) したがって、共同監護の実現、面会交流の促進、子の連れ戻し及び養育費の支払いの促進円滑化といった効果を期待して離婚後双方親権の導入を主張するのは、離婚後双方親権の本質を見誤った議論であって、これらの理由は離婚後双方親権を導入する理由にはならない。
離婚後も協力関係にある父母において、共同で子の監護することは現行法でも可能であり、離婚後双方親権を導入すべきとする立法事実は認められない。むしろ、離婚後双方親権を導入することは、高葛藤やDVなどによる支配・被支配の関係にある父母間において、弊害が大きい。 -
結語
以上のとおり、離婚後双方親権は、期待される効果が乏しいか抽象的であるのに対し、懸念される悪影響は重大かつ確実に生じると思われるのであるから、今般の見直しにおいて導入されるべきではない。
法制審議会家族法制部会での議論状況をみると、あたかも離婚後双方親権を導入することを既定路線として扱っているかのようにも見えるが、仮にそのような方向性で取りまとめを行おうとしているのであれば、将来に重大な禍根を残すことになる。多くの離婚や家族・子どもの問題に現実に取り組んできた弁護士の団体という立場ゆえに、離婚後双方親権導入に警鐘を鳴らし、再考することを強く求める。
2023年(令和5)年11月21日
札幌弁護士会
会長 清 水 智